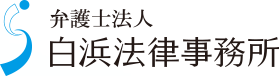2017/12/20
法科大学院の未修枠目標の撤廃などについて思うこと
日経新聞の最新の記事によると、文科省としては、法科大学院の改革として、未修者3割の目標を撤回するということである(著作権などの問題があるので、引用は控える。)。要するに縮小するということなので、そのこと自体は、よいことのように思う。しかし、元々1年で法律の基礎を習得させるという制度設計自体に無理があったのであって、未修の枠を撤廃するというよりは、未修という制度そのものを撤廃した方がよいのではなかろうか。法的知識が不足している人も入学できるようにするとしても、3年かかって卒業する学生と2年で卒業することを予定する学生とに分けるぐらいにすべきであって、それぞれ、法的素養についても入学試験で審査するようにして、法的思考になじまないような人や法的素養が全くないような人までも法科大学院に入れるということではなくすようにするべきだろう。多様な人材を法曹界に確保するという目標があったとしても、法律家としての個別の事案分析や判断に問題があるような人材までも法曹界に入れるべきだというようなことではないはずだし、他の分野から参入したいと考えるような人達であれば、法律の勉強を全くしないままに参入できるなどと考える人はいないはずなので、このような改革が行われたとしても多様な人材が確保できないということにはならないはずである。現状で、他の分野からの法曹への参入が減っているのは、未修という制度に問題があるからではなく、弁護士を激増させすぎたがために、就職難や収入の激減などまで生じて、弁護士の職業的魅力が大きく減退したことが原因である。これは、需給調整をすればよいだけの話で、制度設計を大きく変える必要もない。
なお、この日経新聞の記事によると、「未修者の質を確保して司法試験の合格率上昇につなげたい」との説明があったということのようだが、おかしな話のように思う。法科学院に求められているのは、優秀な法曹の養成であって、司法試験予備校のように司法試験の合格率を上げることではないと思われるからである。試験に合格さえさせればよいということでは困る。また、司法試験の合格率の問題は、個々の法科大学院の個別目標であって、司法試験全体としての合格率を安易にいじることはよろしくない。安易に合格率を緩めることは司法試験の選抜能力を引き下げてしまうことであり、優秀な人材の確保という点での問題が生じることになってしまうからである。未修という制度の下での未修者の司法試験合格率を高めようとすれば、法科大学院に入学させる時点での選抜を強化するか、あるいは、家庭教師のような個別指導に近い徹底的な指導強化しかないが、後者のような方式であれば、授業料等が相当高いものにならないと、採算に合わない制度となってしまう。いずれにしても、個々の法科大学院の努力目標であるべき司法試験の合格率の向上を、制度設計に関わる文科省が口にするのは、学校の先生が試験をやさしいものにしてしまいましょうかと言っているようなものだから、文科省が司法試験の合格率について言及するのはいかがなものかと思う。
また、この記事の背景となっているものと思われる法科大学院等特別委員会(第83回)の配付資料中の「法科大学院等の教育改善について(論点と改善の方向性)(案)」の中に、「時間的負担軽減のため、法科大学院在中の司試験受験をはじめ、司法試験の在り方についても検討するべきではないかとの指摘についてどのよう考えるか 。」との指摘があったことが気になった。在学中に受験を認めるべきことは学生の立場からして当然のことであり、これを認めない制度設計そのものが欠陥なのだから、検討が行われたことは喜ばしいことである。ただ、これが時間的負担軽減のためと断定されているのはおかしいように思う。卒業後に司法試験を受けて、合格後に司法修習開始ということであれば、必然的に無職者を生み出すことになるという問題は極めて深刻な制度的欠陥であると私は思うのである。大学受験浪人であればまだ十代であるが、法科大学院の卒業生は二〇代後半となる人もかなりの割合となる。そんな時期に無職となること自体問題のように思う。アルバイトなども難しいはずである。自分が学生の親であるとすれば、どう思うのだろうか。採用する側としても、アルバイトなどしている時間があれば、さっさと修習を経て、実務に就いて、OJTに励んでもらいたいと思う。二十代半ばに無職となる時期をあえて設けなければならない制度設計とする理由は全くない。この問題は学生や保護者の立場に立って考えるべきことであろう。
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/041/siryo/__icsFiles/afieldfile/2017/11/27/1398626_010.pdf