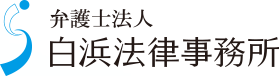日経新聞で、「魅力ある法曹を取り戻そう」との論説が掲載された。その中に、「修了者の7~8割が法曹資格を得るとの見込みは外れ、毎年の司法試験の合格率は2割台に低迷したままだ」との記述があった。これは、第1に、法科大学院修了者のかなりの者がほとんど合格できる制度が実現できなかったことが問題であるとの指摘を含んでおり、第2に、合格率が低かったことが問題であるとの指摘も含んでいると言える。しかし、法科大学院修了者のほとんどを合格させるような仕組みは最初から作られていなかったから、第1の指摘は見当外れのものとなっている。第2の合格率が低いことを問題とする指摘は論理必然的に現状の受験者数が多すぎるか合格者数が少なすぎるという指摘を含んだものとなるところ、少なくとも現状の合格者数は、司法修習生の就職難からして市場の需要に適合していないということと矛盾してしまっている。なお、この司法試験の合格率を問題とする考えは、法科大学院側で自らの努力を棚に上げて責任転嫁しようとする論理であるということについては、以前に分析させていただいたところであるが、この論説は、矛盾が目立つところがあるので、以下、具体的に反論を加えてみることにする。
まず、修了者の7~8割が法曹資格を得るということにするのであれば、法科大学院の卒業者が司法試験合格者の1.3倍ほどしかないという制度設計にならなければ成り立たない。つまり、極めて厳しい選抜試験を法科大学院入学に際して要求し、法科大学院入学者を卒業させるかどうかの判定も厳しいものにして、卒業生が司法試験合格者の1.3倍ぐらいになるまで絞り込まねばならない。ところが、法科大学院では未修者は法的素養を問うことなく合格させるという仕組みが採用されている。修了者が目指す司法試験では法的素養が問われることになっているので、司法試験に合格するような人を選抜するための厳しい入学選抜の仕組みがそもそも法科大学院には存在していないことになる。では、卒業させるかどうかで絞ればいいのではないかということになるが、入学させて学費も払わせておきながら卒業はさせないというような学校など、誰も入学しないだろうということになるのは必然なので、卒業させるかどうかで絞ることなど机上の空論ということになってしまい、現に、今の法科大学院では大幅に卒業生を絞るようなことは行われていない。他方で、法科大学院の設置や定員の絞りについては、大学の自治もあるから、国家政策としての絞り込みはそもそも無理がある。できるとしてもせいぜい補助金の制限ということになってしまう。では、問題とされている法科大学院の乱立が問題だったのかということについて考えてみた場合、法科大学院が創設された2004年(平成16年)の前年である2003年(平成15年)の司法試験受験者数は、史上最高の50,166人ということだったし、実際にも定員不足となったような法科大学院が当初から出現したようなことは聞いたこともないから、少なくとも設置を求める程の入学希望者すなわち社会的需要は存在したのであって、法科大学院の絞り込みができる社会状況にあったとは到底言えないように思われる。要するに、法科大学院制度は、最初から「修了者の7~8割が法曹資格を得る」という仕組みでは作られていないのである。日経新聞の論説を書かれた方は、このことを意図的に無視されているのではなかろうか。しかも、現状では、法科大学院の入学希望者そのものが激減しているので、司法試験の合格率は否が応でも高まるような自然の流れとなっていて、意図的に合格率を下げるようなこともする必要すらなくなってしまっているのである。この論説が、今の段階で合格率のことを問題にするのが何を意図しているのかはますますもってよくわからないことになる。
次に、合格率は受験者数と合格者数によって決まるだけのものであるから、合格率が高いということは受験生の数に比して多くの者が合格するということであり、一般的には簡単な試験ということを意味するし、優秀な人材を選択するという機能が乏しいことも意味することになる。となると、論説委員は、司法試験の合格者は特に優秀でなくてもいいと言っているということになってしまうが、そうでないとすれば、法科大学院において厳しい選抜が行われることを期待しての意見ということになる。しかし、前述したように、法科大学院にはそのような選抜機能は期待できないのであるから、結局のところ、現状の受験者数を前提として、さらに合格者を増やして合格率は高めればよいということなのだろうかということになる。ところが、これでは結果的に、司法試験の選抜機能は低下してもよいということ、すなわち、司法試験の合格者は特に優秀でなくてもよいということを意味することになってしまうし、合格者を現状よりも増やせということは、司法修習生の就職難が恒常化している現状の法曹界の労働市場の現状を無視した主張ということにもなる。では、この論説が修習生の就職難などないと言っているかというと、論説の中では、「弁護士になっても就職難に陥るといった事態を招いた」ということが指摘されてもいるから、現状の合格者数よりももっと多く合格させるべきだとも言い切れていないようでもある。いずれにしても、昨今では法科大学院の入学希望者も激減し、司法試験の受験者も史上最低となる程、法曹は不人気な業種に成り下がり、司法試験の合格率は結果としての受験者減によって高くなり、全入に近い状態になることすらあり得る事態となっているということに対して、この論説は何らの提案もしていないように思われる。
もっとも、この論説は、「貧困や介護の現場、虐待・ストーカー被害など、法律の目が届いていない分野はまだある。」とも指摘し、一見すると積極的な提案があるかのようにも思えなくもないが、これらが公的補助なしにビジネスとして成り立つ事業分野なのか、事例としてどれだけの弁護士を必要とする分野なのかなどは全く検討されていないようである。要するに思いつきを述べているだけのことであって、具体的な解決策とはなっていない。論説は続けて「ビジネスの世界でも、知的財産をめぐる紛争やコンプライアンスの徹底など、法律家の活躍が期待される機会は多い。」とも指摘しているが、この分野への弁護士の進出は既にかなり進んでいるにも関わらず、「弁護士になっても就職難に陥るという事態」となっていることはあえて無視されているようでもある。
以上指摘させていただいたとおり、私としては、矛盾ばかりが目立ち、文章の論理構成の検討不足が甚だしい論説であるので、あえてブログで批判させていただいた次第である。
なお、法曹養成をめぐる政策、特に「新司法試験の合格者数3000 人/年,法科大学院修了者の7~8 割の合格」や合格率の問題については、武蔵大学の木下富夫教授の「法曹養成メカニズムの問題点について-経済学的観点から」(日本労働研究雑誌2010年1月号)にて詳しく論じられていて、参考になる。ネットで公開されているから、検索してもらえれば、すぐにたどり着くことができる。木下教授がこの論稿を公開された2010年の時点より、法曹の労働市場はさらに悪化しており、結果的に受験生からも見放され、受験者数は法科大学院だけでなく司法試験ですら大きく減ってきている。法曹養成制度改革はまさに喫緊の課題であり、思いつきを提案してどうにかなる状態ではなくなりつつあるのである。