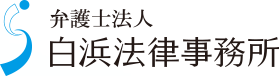2019/03/17
法曹養成制度の改革は法科大学院救済ありきで進めてはいけないのでは?
法曹養成制度の改革が待ったなしの状況に置かれていることについては、ほとんどの人が異論のないところであろう。最大の問題点は、法曹志願者の減少である。大学の文系科目の花形のような存在であった法学部の志願者が減少し、東大では文Ⅰが文系最難関ではなくなってしまったというのであるから、法曹志願者の最大の基盤である法学部の優秀な学生の層が減少してきているほど事態は深刻である。法曹の最大の供給源である大学法学部の人気が落ちているということだと、法曹志願者の減少を回復させることはしばらくは見込めないだろうから、法曹志願者の回復は急務となっていると言えよう。
この法曹養成の問題では政府案が新たに示され、京都新聞でも、平成31年3月15日に社説が発表され、この政府案への批判的意見が示されている。しかし、この社説にはいくつか指摘せざるを得ない点がある。
まず指摘せねばならないことは、法科大学院の救済という視点を重視している点は果たしてどうなのかということである。今、最も重視せねばならないところは、法曹志願者の減少に歯止めをかけて、その回復を目指すということであって、法科大学院の救済は、法曹志願者の回復のためにも有効であるということが検証された後で検討されるべきことではなかろうか。また、そもそも法科大学院制度そのものがどうだったのかということを検証しないままに、法科大学院の救済を目指すことが果たしていいことなのかということも冷静に考えるべきことのように思う。
法科大学院は、法曹養成の基幹となるべきものとして期待されて設置されたものが、当初より、司法修習の前記修習の代わりすらできず、いつの間にかそのような役割はそもそもできなかったと開き直りのような発言が堂々と法科大学院関係者から行われ(平成24年4月24日開催の法曹の養成に関するフォーラム第13回会議中の井上正仁発言)、結果的に司法修習では前期修習に近い集合修習を復活させねばならなくなり、実務修習期間の短縮を余儀なくされるに至っている。つまり、法科大学院は、当初より、法曹養成の基幹となるだけの教育を学生に施すことができていなかったとの評価を受けてもおかしくなく、それが故に司法修習制度まで変更を余儀なくされているという事実がまずは議論の前提とされるべきもののように思う。
この点、私は、元々、法科大学院に法曹養成の基幹となるような役割を期待することには無理があったと思っている。そもそも「未修」という、法律の知識も不足し、法律家的思考に適しているかどうかもわからないような学生を受け入れることが求められている上、最終的な法曹資格者を選別する司法試験の合格者数と比してはるかに多い数の学生を受け入れて教育するということになっているために、卒業生の中には法曹にならない人の方がむしろ多いような常態での教育を強いられる構造が法科大学院にはあるからである。つまり、その構造上、法科大学院は、法曹そのものの養成ではなく、法曹となろうとする人への学びの場を提供しているに過ぎないのであって、法曹養成の基幹的役割を期待することは制度的に無理があったと思うのである。井上正仁発言は、まさにこのことを正直に告白した発言ととらえると理解しやすいように思う。
しかも、司法試験の受験資格が法科大学院の卒業ということにされたことで、法曹志願者は、法科大学院を卒業して無職状態で社会に一度放り出された上で、司法試験への合格を個人的努力で目指さなければならないことにされてしまった。大学の場合、現役合格が原則であるが、司法試験の場合、浪人以外の選択はないこととされてしまったわけである。このことで、法科大学院は司法試験予備校よりも無責任な立場とされてしまっているように私には思える。これも、法科大学院が法曹養成の基幹となれていない原因の一つではなかろうか(私は、上記の構造的欠陥を修正すると言う意味でのギャップタームの解消、つまり、在学中の司法試験受験を法科大学院生に認めることは好ましい改革なのであって、決して非難されるようなことではないと考えている。)。
次に、法科大学院を救済すれば、法曹志願者が戻るかということであるが、法科大学院を救済しても志願者が戻ることはないことは明らかである。そもそも志願者が減少した原因は、法曹需要の予測の誤りにあって、法科大学院の卒業生が実際に法曹となる前の段階から、就職難を発生させてしまい、その後は弁護士の就職難ということが社会にも広く知れるようになってしまったということにある。資格を得て仕事に就くための試験が司法試験である以上、至極当然のことである。従って、司法試験の合格者を減らして、就職難や就職後の将来への不安を取り除くことがまずは最優先課題とされるべきである。ところが、このように司法試験合格者数を減らすことは、法科大学院にとって、卒業生の司法試験合格確率が減るということに直結するということで、法科大学院関係者からは、合格者数の減少に対して強い不満が述べられることになる。しかし、これは本末転倒の議論であろう。職業人の養成を行う以上、その職業の将来展望を抜きにして、とりあえず沢山合格させてくれなどと社会に要求するのは無責任な議論のように思う。大学医学部の教育者の中では、自分達の学生を合格させたいから医師試験全体の合格者数を増やしてくれなどと言われていることはないと思うが、法学部だけは別の論理がまかり通るということではなかろう。
前述した京都新聞の社説では、予備試験を非難しているように思えるが、法科大学院の教育実態の検証もされないままに、予備試験を制限して法科大学院を優遇することは、本松転倒の議論のように思える。むしろ、予備試験と法科大学院は対等な競争関係におくべきであろう。法科大学院が学生を呼び戻したいのであれば充実した教育を行って学生から支持されるように努力したらいいのではないか。法科大学院関係者は、その卒業生の経済的負担の軽減に直結する司法修習の給費制復活にすら自らの予算確保のために反対し、司法修習生の負担を強く求めたぐらいであるから、学生が集まらないことで自らの経営問題が生じたとしても自助努力に励んで自力解決することは当然のように思う。むしろ、現状では、予備試験があることで、経済的な負担もなく自ら独学で法律の勉強に励もうとする学生にも法曹となれる機会が広がっているのであるから、予備試験は法曹志願者の減少をくい止めているとさえ言うことができるのであって、この制限は、かえって、法曹志願者の減少につながる危険性が極めて高い。実際、雇う側の弁護士や裁判所検察庁でも、予備試験合格組を多く採用している傾向にあり、法科大学院卒業生でなければ採用しないというようなことにはなっていない。裏返せば、雇う側からすれば、予備試験合格者の評価は高いということであり、法科大学院での教育を受けたかどうかが採用にあたっての有利な要素になることができていないということである。これは、決して軽視されるべきではない。結局のところ、予備試験制限には何らの合理的根拠もないと思う。
また、社説では、法科大学院の予備校化を懸念しているようであるが、予備校がなぜ非難されるべきなのかが、私にはわからない。昔から予備校は存在しているし、むしろ、大学の授業では司法試験にはなかなか合格できないということではなかったと思う。反省が行われるべきは、大学や法科大学院の教育の方ではなかろうか。司法試験の合格に実績を上げている予備校が非難されるいわれはないだろうし、むしろ、法科大学院が予備校よりも学生から支持される教育を行うことができているかということが検証されるべきことではないかと私は思う。
最後に、京都新聞の社説には、弁護士の都市部偏在が法科大学院の設置によってもたらされたかのような記述があることも気になった。この記述が、法科大学院の設置によって、弁護士過疎地域が出現したと理解されているのであればそれは誤解である。弁護士ゼロワン地域の解消は、法科大学院の卒業生が司法試験に合格する前に実現している。法科大学院制度の設置に伴い法曹資格者が激増することにはなったのだが、そのことによってゼロワン地域が復活したというようなことはない。弁護士ゼロ地域であった宮津京丹後地域を抱える京都府では、公設事務所の設置などで全国に先駆けてゼロワン地域の解消を実現したのであるが、そのことが地元の新聞社に理解されていなかったとすれば、少し残念である。
なお、この社説が、最近の弁護士の就職の傾向として、地方の弁護士会への入会者が減っているということを問題としているのであれば、果たしてそれが大きな問題なのかということを指摘しておきたい。人口過疎地域での弁護士会の法律相談が相談枠が満杯となっているような事実はなく(むしろ充足率の低さが問題となっているほどである)、地方での弁護士不足の声はほとんど聞こえてこないからである。
いずれにしても、これまでの法曹養成制度の改革は、大学関係者の声が過度に重視されて、理念に先走る傾向があるように思う。実際に法科大学院で教育を受けた人間である若手の弁護士や、弁護士を雇い入れている弁護士を初めとして、裁判所や検察庁などの現場の声にもっと耳を傾けた地道な改革を目指してほしいと思うのである。